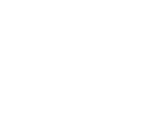淡路島の古民家での暮らし方_File20
2018.3.6
Researchの概要
調査日2018年3月6日

File20 新庄 道 shinjo naoshi
新庄 道 shinjo naoshi
人目線ではなくもっと大きな視野で、人と自然が良い関係を築いていくために、Hikobae worksを立ち上げる。里山や森の環境整備のために木を伐採し、伐り出した木は、材としてものづくりをする作家などに供給している。
蘖(ひこばえ)のように土地に根付いた文化や伝統に学び、現代に合う方法で実践している。
手づくりの暮らし







山桜や桃が開花し始め、華やかな季節ががいよいよ目に見えるかたちで現れてきたころ、彼の住む古民家を訪ねた。洲本の市街地から山の方へ車を走らせること15分ほど。車が2台すれ違うことのできない細い道から、さらに細い橋を渡ったところ、背には2つの山がそびえる場所に彼が暮らす立派な門構えの日本家屋はあった。ガスなどのライフラインは引いておらず、かつての日本人の暮らしでは当たり前だった薪と井戸で暮らしを立てている。今年で4年目となるここ淡路島での暮らしは、最初は6人で始まり多いときは10人で暮らしていたこともあるそう。現在は彼と他に大人2人子供1人の合わせて4人で共同生活をしている。
門を入ると、カラフルな赤や黄色のドラム缶やコンテナがここそこに置かれていたり、薪にするために朝の散歩で拾ってきたという細い枝が山積みになっていたり、かつて応接間におかれていたような立派だが、くたびれたソファもいくつか並べられている。さらに足元を見ると、鹿のかわや骨がその辺に落ちていたりする。そこに規則性はなく様々な人が暮らしていることがそこからうかがえる。見渡すと山が広がり、ここで暮らすことはなんだか自然に受け入れられているような感覚になる。お互いを認め合い、許し合えているような、そんな親密さが感じられた。
玄関戸を開けると、土間が広がり共同スペースとなるカウンターテーブルと椅子があり、ロケットマスヒーターを備えた小上がりのくつろぎのスペースがある。自然と人が集まり、寄り添うように暮らしている様子が見て取れる。
異国で直面した自国の災害













新庄さんが今の暮らしをするようになる始めの小さな種は、大学時代まで遡る。
大学でアフリカの飢餓の問題について興味を持ち、ネリカという乾燥地帯でも育つ稲の研究に没頭するようになる。3回生の頃単身アフリカへ渡り、ダウンタウンで地元の方の板金の仕事を手伝いをしながら、作物を作る生活をしていたそう。そんな時に、ほぼ地球の反対側の故郷日本で、未曾有の大災害が起こった。3.11東日本大震災である。誰も経験したことのないような自然災害、それに伴う原発問題などの人的災害。彼は、遠く離れたアフリカの地で、日本での問題に直面することになる。
今起こっている問題は、決して遠く離れたアフリカにいる自分には関係のない話ではなく、アフリカが抱える問題も自国(先進国)で起こった問題も違いはないのではないか。まずは自国、日本でのこの問題を自分たちがどうにかする方が先なのではないか。との想いで帰国。そうして原発反対運動や、ハンガーストライキなど過激な活動に参加するようになる。しかし次第に考え方は変わり、大きく声をあげるよりも自分たちが健やかに暮らせることが重要で、そこから少しずつ変わって行くのではとの思いに至る。
「自分たちが健やかに暮らせることが一番。環境にいい暮らしもいいけれど、そこに暮らす人々が納得して健やかに暮らせることが一番大切なこと。」そうした経緯があり、コミュニティを作りその中で自分たちの暮らし方を手探りしながら共同生活を始めていく。デモクラティックの考え方の元に、そこにいる人々が年齢や性別、立場など関係なく、自分たちで考え、話し合い、ともに健やかに暮らす方法を実践している。
蘖(ひこばえ)







現在新庄さんは林業がないと言われている淡路島で、木を伐ることを生業としている。しかしそれは、例えば太陽光パネルを設置するために山を切り開いたり、人目線で邪魔となる木を伐採することが多かったそう。自然と対峙し、木を伐る職業を選択した彼の中にもやもやとした疑問が徐々に大きくなっていった。人目線ではなく、もっと大きな視野で人と自然の良い関係性を築いていくための方法を模索するためにHIKOBAE Worksを立ち上げた。
「淡路島は変わった山、価値のある山がある。地元の人が価値を見出すことが未来につながる。この辺りでは、昔は炭作りが行われていて、そのための炭焼き小屋が今も残っている。現代に復活させたい。」と新しい動きに意欲を燃やす。一からタネを蒔いて新しいことを始めるのではなく、土地に根付いた文化や伝統を土台に、そこから学びながら現代にあう方法で実践していこうとしている。蘖(株元から生える新芽のこと)のごとく。
暮らし=趣味










そろそろお昼が近くなってくると、お米を洗ったり、野菜を切ったり、お湯を沸かし始めたりと3者3様それぞれ手を動かし始める。しばらくするといい匂いが漂ってくる。猪肉の煮込みを昨日から準備してくれていたそうだ。3人とも狩猟の免許を持ち、裁くこともできるという、ツワモノ揃い。お米も共同の田んぼで作っているし、家のそばには小さな畑を持ち、季節ごとの野菜も育てている。今日の野菜は、八百屋の友人からのおすそ分けだそうだが、自分たちの周りでほぼ賄えているそうだからなんと豊かなことだろう。まだ春の入り口に一歩踏み出したくらいの時期なので、薪ストーブの上に並ぶ鍋から立ち上る湯気や、パチパチと爆ぜる薪の音になんとも幸せな気持ちになる。ともすると、不便という一言でかたずけられそうなものを、彼らは楽しんでいる。
ここでは本当に暮らすことに時間がかかる。一方視点を変えてみてみれば、時間がゆっくり流れているとも言える。非効率なようでそうではないようだ。スローライフと言われるけれど、本当はめっちゃビジーライフなんですと笑う。
時間軸や、効率などの物差しでは測れない、豊かさや健やかさがたくさんあふれている。暮らし=趣味と言ってしまうあたりに、彼らの暮らしの充実ぶりが見て取れる。







山桜や桃が開花し始め、華やかな季節ががいよいよ目に見えるかたちで現れてきたころ、彼の住む古民家を訪ねた。洲本の市街地から山の方へ車を走らせること15分ほど。車が2台すれ違うことのできない細い道から、さらに細い橋を渡ったところ、背には2つの山がそびえる場所に彼が暮らす立派な門構えの日本家屋はあった。ガスなどのライフラインは引いておらず、かつての日本人の暮らしでは当たり前だった薪と井戸で暮らしを立てている。今年で4年目となるここ淡路島での暮らしは、最初は6人で始まり多いときは10人で暮らしていたこともあるそう。現在は彼と他に大人2人子供1人の合わせて4人で共同生活をしている。
門を入ると、カラフルな赤や黄色のドラム缶やコンテナがここそこに置かれていたり、薪にするために朝の散歩で拾ってきたという細い枝が山積みになっていたり、かつて応接間におかれていたような立派だが、くたびれたソファもいくつか並べられている。さらに足元を見ると、鹿のかわや骨がその辺に落ちていたりする。そこに規則性はなく様々な人が暮らしていることがそこからうかがえる。見渡すと山が広がり、ここで暮らすことはなんだか自然に受け入れられているような感覚になる。お互いを認め合い、許し合えているような、そんな親密さが感じられた。
玄関戸を開けると、土間が広がり共同スペースとなるカウンターテーブルと椅子があり、ロケットマスヒーターを備えた小上がりのくつろぎのスペースがある。自然と人が集まり、寄り添うように暮らしている様子が見て取れる。













新庄さんが今の暮らしをするようになる始めの小さな種は、大学時代まで遡る。
大学でアフリカの飢餓の問題について興味を持ち、ネリカという乾燥地帯でも育つ稲の研究に没頭するようになる。3回生の頃単身アフリカへ渡り、ダウンタウンで地元の方の板金の仕事を手伝いをしながら、作物を作る生活をしていたそう。そんな時に、ほぼ地球の反対側の故郷日本で、未曾有の大災害が起こった。3.11東日本大震災である。誰も経験したことのないような自然災害、それに伴う原発問題などの人的災害。彼は、遠く離れたアフリカの地で、日本での問題に直面することになる。
今起こっている問題は、決して遠く離れたアフリカにいる自分には関係のない話ではなく、アフリカが抱える問題も自国(先進国)で起こった問題も違いはないのではないか。まずは自国、日本でのこの問題を自分たちがどうにかする方が先なのではないか。との想いで帰国。そうして原発反対運動や、ハンガーストライキなど過激な活動に参加するようになる。しかし次第に考え方は変わり、大きく声をあげるよりも自分たちが健やかに暮らせることが重要で、そこから少しずつ変わって行くのではとの思いに至る。
「自分たちが健やかに暮らせることが一番。環境にいい暮らしもいいけれど、そこに暮らす人々が納得して健やかに暮らせることが一番大切なこと。」そうした経緯があり、コミュニティを作りその中で自分たちの暮らし方を手探りしながら共同生活を始めていく。デモクラティックの考え方の元に、そこにいる人々が年齢や性別、立場など関係なく、自分たちで考え、話し合い、ともに健やかに暮らす方法を実践している。
蘖(ひこばえ)







現在新庄さんは林業がないと言われている淡路島で、木を伐ることを生業としている。しかしそれは、例えば太陽光パネルを設置するために山を切り開いたり、人目線で邪魔となる木を伐採することが多かったそう。自然と対峙し、木を伐る職業を選択した彼の中にもやもやとした疑問が徐々に大きくなっていった。人目線ではなく、もっと大きな視野で人と自然の良い関係性を築いていくための方法を模索するためにHIKOBAE Worksを立ち上げた。
「淡路島は変わった山、価値のある山がある。地元の人が価値を見出すことが未来につながる。この辺りでは、昔は炭作りが行われていて、そのための炭焼き小屋が今も残っている。現代に復活させたい。」と新しい動きに意欲を燃やす。一からタネを蒔いて新しいことを始めるのではなく、土地に根付いた文化や伝統を土台に、そこから学びながら現代にあう方法で実践していこうとしている。蘖(株元から生える新芽のこと)のごとく。
暮らし=趣味










そろそろお昼が近くなってくると、お米を洗ったり、野菜を切ったり、お湯を沸かし始めたりと3者3様それぞれ手を動かし始める。しばらくするといい匂いが漂ってくる。猪肉の煮込みを昨日から準備してくれていたそうだ。3人とも狩猟の免許を持ち、裁くこともできるという、ツワモノ揃い。お米も共同の田んぼで作っているし、家のそばには小さな畑を持ち、季節ごとの野菜も育てている。今日の野菜は、八百屋の友人からのおすそ分けだそうだが、自分たちの周りでほぼ賄えているそうだからなんと豊かなことだろう。まだ春の入り口に一歩踏み出したくらいの時期なので、薪ストーブの上に並ぶ鍋から立ち上る湯気や、パチパチと爆ぜる薪の音になんとも幸せな気持ちになる。ともすると、不便という一言でかたずけられそうなものを、彼らは楽しんでいる。
ここでは本当に暮らすことに時間がかかる。一方視点を変えてみてみれば、時間がゆっくり流れているとも言える。非効率なようでそうではないようだ。スローライフと言われるけれど、本当はめっちゃビジーライフなんですと笑う。
時間軸や、効率などの物差しでは測れない、豊かさや健やかさがたくさんあふれている。暮らし=趣味と言ってしまうあたりに、彼らの暮らしの充実ぶりが見て取れる。







現在新庄さんは林業がないと言われている淡路島で、木を伐ることを生業としている。しかしそれは、例えば太陽光パネルを設置するために山を切り開いたり、人目線で邪魔となる木を伐採することが多かったそう。自然と対峙し、木を伐る職業を選択した彼の中にもやもやとした疑問が徐々に大きくなっていった。人目線ではなく、もっと大きな視野で人と自然の良い関係性を築いていくための方法を模索するためにHIKOBAE Worksを立ち上げた。
「淡路島は変わった山、価値のある山がある。地元の人が価値を見出すことが未来につながる。この辺りでは、昔は炭作りが行われていて、そのための炭焼き小屋が今も残っている。現代に復活させたい。」と新しい動きに意欲を燃やす。一からタネを蒔いて新しいことを始めるのではなく、土地に根付いた文化や伝統を土台に、そこから学びながら現代にあう方法で実践していこうとしている。蘖(株元から生える新芽のこと)のごとく。










そろそろお昼が近くなってくると、お米を洗ったり、野菜を切ったり、お湯を沸かし始めたりと3者3様それぞれ手を動かし始める。しばらくするといい匂いが漂ってくる。猪肉の煮込みを昨日から準備してくれていたそうだ。3人とも狩猟の免許を持ち、裁くこともできるという、ツワモノ揃い。お米も共同の田んぼで作っているし、家のそばには小さな畑を持ち、季節ごとの野菜も育てている。今日の野菜は、八百屋の友人からのおすそ分けだそうだが、自分たちの周りでほぼ賄えているそうだからなんと豊かなことだろう。まだ春の入り口に一歩踏み出したくらいの時期なので、薪ストーブの上に並ぶ鍋から立ち上る湯気や、パチパチと爆ぜる薪の音になんとも幸せな気持ちになる。ともすると、不便という一言でかたずけられそうなものを、彼らは楽しんでいる。
ここでは本当に暮らすことに時間がかかる。一方視点を変えてみてみれば、時間がゆっくり流れているとも言える。非効率なようでそうではないようだ。スローライフと言われるけれど、本当はめっちゃビジーライフなんですと笑う。
時間軸や、効率などの物差しでは測れない、豊かさや健やかさがたくさんあふれている。暮らし=趣味と言ってしまうあたりに、彼らの暮らしの充実ぶりが見て取れる。