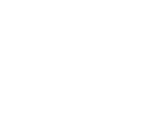鮎屋の植生_File01
2025.3.24
Researchの概要
調査日 2025年3月17日
洲本市にある鮎屋の滝と鮎屋ダム周辺の植生の調査

ヤブツバキ
camellias japonica
ツバキ科 離弁花 常緑高木
分布 本州〜九州
高さ 5m
ヤブツバキは照葉樹林の樹木の代表であり、日本に自生する野生の椿である。
今の時期は開花しており見つけやすい。葉は厚くツヤがあり、ふちに小さな鋸歯がある。
今の時期は開花しており見つけやすい。葉は厚くツヤがあり、ふちに小さな鋸歯がある。
鮎屋の滝でもダム周辺でもたくさん自生している。

ヤマビワ
Meliosma rigida Siebold et Zucc.
アワブキ科 常緑小高木
分布 本州(静岡県以西)〜九州、沖縄 の山地
高さ 7~10m
兵庫県レッドデータブック ランクC 2020
ビワの葉の形に似ており、日陰を好んで自生している。
若枝、花序、葉柄および葉裏に褐色の綿毛が密生する。
葉は互生し、葉先に粗鋸歯があり、先端が細く伸びている倒披針形。
神社の儀式などで火おこしの道具として、ヒノキの板とヤマビワの枝が使われる。
若枝、花序、葉柄および葉裏に褐色の綿毛が密生する。
葉は互生し、葉先に粗鋸歯があり、先端が細く伸びている倒披針形。
神社の儀式などで火おこしの道具として、ヒノキの板とヤマビワの枝が使われる。

ナンカイアオイ
Asarum nipponicum var. nankaiens
ウマノスズクサ科 常緑多年草
分布 和歌山県、兵庫県淡路島、徳島県、高知県、香川県
絶滅危惧II類(VU)(2017年環境省)
山地の林床に生育しており、根茎は多肉で節が多く、地を這う。葉は卵形で長さ6〜10㎝、基部は深い心形で、上面は濃緑色で白斑があるものが多い。10〜2月ころに地面近くに短い柄をだし、2㎝ほどの暗紫色の花をつける。

アリドオシ
Damnacanthus indicus
アカネ科 常緑低木
分布 本州(関東以西)〜九州、沖縄
山地のやや乾いた薄暗い林下に生育する。
枝から伸びるたくさんの鋭い棘があり、蟻を刺すと言われることから名前が付けられている。5月ごろに白い花を咲かせ、冬に赤い実をつける。葉は対生し、葉の付け根部分から長さ1〜2cmほどの棘が伸びている。
枝から伸びるたくさんの鋭い棘があり、蟻を刺すと言われることから名前が付けられている。5月ごろに白い花を咲かせ、冬に赤い実をつける。葉は対生し、葉の付け根部分から長さ1〜2cmほどの棘が伸びている。

ハナミョウガ
Alpinia japonica
ショウガ科 常緑低木
分布 本州(関東以西)〜九州、奄美大島
山地のやや湿った林下に生育する。葉が茗荷の葉とよく似ている。
葉はいい香りで、芳香成分はシネオール、β-ピネン、樟脳、セスキテルペンなどが含まれる。種子は乾燥させ、主に健胃の効果を持つ薬として使用される。
葉はいい香りで、芳香成分はシネオール、β-ピネン、樟脳、セスキテルペンなどが含まれる。種子は乾燥させ、主に健胃の効果を持つ薬として使用される。

カンザブロウノキ
Symplocos theophrastifolia
ハイノキ科 常緑の小高木。
分布 本州(静岡県以西)〜九州、琉球諸島
高さ 10m
兵庫県レッドデータブック2020 Aランク
葉は互生し、先端は次第に細くなって尖った長い楕円形。葉縁には低いきょ歯がある。鹿にとって、不嗜好性植物とされている。
葉は互生し、先端は次第に細くなって尖った長い楕円形。葉縁には低いきょ歯がある。鹿にとって、不嗜好性植物とされている。
「神さぶる」という古語が語源という説があり、伊勢神宮の宮域全体に1万本余りも植えられているそう。

ツルコウジ
Ardisia pusilla
サクラソウ科 下部が蔓性の小低木
分布 本州(千葉県以西)〜九州、沖縄
高さ 5〜10cm
兵庫県レッドデータブック2020 Cランク
高さは5~10cmほどで、茎がつる状で横に這うように伸びていく。茎には赤褐色の長い軟毛が密生している。
葉は3~5枚が輪生状に互生する単葉で、縁には粗い鋸歯がある。
果実は冬に赤く熟し、春まで見られる。
高さは5~10cmほどで、茎がつる状で横に這うように伸びていく。茎には赤褐色の長い軟毛が密生している。
葉は3~5枚が輪生状に互生する単葉で、縁には粗い鋸歯がある。
果実は冬に赤く熟し、春まで見られる。

タイミンタチバナ
Myrsine seguinii
サクラソウ科 常緑小高木
分布 本州(千葉県以西)〜九州、沖縄
高さ 5〜10cm
兵庫県レッドデータブック2020 Cランク
葉は枝先に集まって互生し、先端が尖った線状長楕円形。
花は3~4月に、前年枝の葉腋に淡緑白色または淡黄色の花を3~10個束生する
名前の由来は、明の国(中国)に産するタチバナの意で、中国原産と思い違いしたそう。
家畜の駆虫剤としてや、タンニンが含まれるため染料としても使用されていた。
家畜の駆虫剤としてや、タンニンが含まれるため染料としても使用されていた。

タイミンタチバナ
鮎屋ダム周辺で観察したもの。道端の日当たりの良い斜面地に生息しており、花付きがよく、葉も青々と繁っている印象。

ホルトノキ
Elaeocarpus sylvestris
ホルトノキ科 常緑高木
分布 本州(千葉県以西)〜九州、沖縄
高さ 10〜15m
緑の葉の中に赤い葉が混じっているのが特徴(年中)
名前の由来は「ポルトガルの木(オリーブの木)」から来ており、平賀源内が、紀州でこの木をみてオリーブと勘違いしたことから、この木がホルトノキといわれるようになったといわれている。

ミミズバイ
Symplocos glauca
ハイノキ科 常緑小高木
分布 本州(千葉県以西)〜九州、沖縄
高さ 10〜15m
葉は枝先に集まって互生し、先端が尖った狭長楕円形である。
燃やして出来た灰を染物の媒剤としても利用する。
伊勢神宮では神饌供進の際に葉を食べ物の下敷きとして用いられる。
伊勢神宮では神饌供進の際に葉を食べ物の下敷きとして用いられる。

キブシ
Stachyurus praecox
キブシ科 落葉低木
分布 北海道、本州〜九州、沖縄、小笠原
高さ 3〜5m
日本固有種。キブシの開花は新葉が展開する前の3~4月。前年に伸びた枝に小花の密集した花穂がぶら下がる。小花は直径7ミリほどの鐘型。
果実はタンニンを多く含み、染料の原料である五倍子(ふし)の代用として使ったことから木五倍子(きぶし)と名付けられた。

サカキカズラ
Anodendron affine
キョウチクトウ科 常緑蔓性低木
分布 北海道、本州〜九州、沖縄
他の樹木に巻き付いて伸びる。
袋果はかたく一対の円柱状、種子には長い毛がついていて風で散布される。一対の袋果に、20~30個ほどの綿毛が入っている。
鮎屋ダム周辺を散策中に種子が風に乗って飛んでいく様子が何度も見られた。花期は4~5月ごろ。

フユザンショウ
Zanthoxylum armatum
ミカン科 常緑低木
分布 北海道、本州〜九州、沖縄
高さ 2~3m
山椒は冬に落葉するが、冬山椒は一年中葉が残っている。
葉は奇数羽状複葉で互生し、葉柄には翼がある。
芳香性が無いので食用としては利用されないが、漢方では痰や咳など生薬として用いられる。