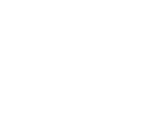植生の調査_File05_猪ノ鼻ダム周辺(柏原山)
2025.8.25
Researchの概要
柏原山(かしわらやま)は、淡路島南東部、諭鶴羽山地東部にある標高568.9mの山で、洲本市千草丙に位置する。諭鶴羽山(ゆずるはさん)、先山(せんざん)とともに「淡路三山」の一峰をなす。
今回は猪ノ鼻ダム周辺の植生を調査する。
猪ノ鼻ダムは、洲本市の最初の上水道用ダムとして、昭和9年に完成し給水を開始している。
Mt. Kashihara is a 568.9-meter-high mountain located in the eastern part of the Yuzuruha Mountains in southeastern Awaji Island, within Chikusasahei, Sumoto City. Together with Mt. Yuzuruha and Mt. Senzan, it forms one of the “Three Mountains of Awaji.”
This time, we will survey the vegetation around Inohana Dam.
Inohana Dam, completed in 1934, was the first dam built for water supply in Sumoto City and began supplying water that same year.
調査日2025年8月25日

ノグルミ
Platycarya strobilacea
クルミ科 落葉広葉樹高木
分布 東海以西の本州、四国、九州
高さ 10~20m
葉は互生で、奇数羽状複葉。
果実や樹皮にタンニン成分が含まれており、前者は染料に、後者は革なめしに利用された。
燃やすと沈香のような特有の芳香がある。
また樹皮や枝葉に、水棲生物に有毒なナフトキノンが含まれており、昔は魚を撮る際に、魚毒として用いた。

タラヨウ
llex latifolia
モチノキ科 常緑高木
分布 静岡以西の本州、四国、九州 山地
高さ 10~20m
葉は大きく肉厚で、20cmほどの長楕円形で、葉表は濃い緑色で艶があり、細かい鋸歯がある。
葉の裏を傷つけると黒変するため文字が書ける。昔は、経文をかいたり、情報のやりとりをしたという話もあり、これがはがき(葉書)の語源になったとか。(諸説あり)



ツバキ
Camellia japonica
ツバキ科 常緑小高木
分布 本州、四国、九州、南西諸島の沿岸沿いや山地
高さ 5~10m
日本原産。
椿の実はとても硬い。9月ごろ実が弾け、中の種子から油が取れる。重量の1/3の油が取れると言われ、食用や整髪料として使われる。

フユザンショウ
Zanthoxylum armatum
ミカン科 常緑低木
分布 関東地方以西の本州、四国、九州、沖縄の丘陵帯
高さ 2~3m
日本では雌株しか存在しない。一年枝は、赤褐色で枝や葉柄の基部に対生する棘がある。葉は奇数羽状複葉で互生する。葉柄には翼がある。冬でも葉っぱが落ちない。
果期は8月で、未熟な緑の果実が観察できた。葉や実に芳香性が少なく、サンショウのように食用にはならない。
サンショウ、イヌザンショウに比べて、フユザンショウの葉はだいぶん大きい。

ナガバヤブマオ
Boehmeria sieboldiana
イラクサ科 多年草
分布 関東地方以西の本州、四国、九州、沖縄 山地
高さ 1~2m
カラムシ属の在来種。
花期は7~8月で20cmほどの穂状花序をつける。
鹿が嫌い、葉は食べない。

タケニグサ
Macleaya cordata
ケシ科 多年生草本
分布 本州、四国、九州、琉球諸島
高さ 1~2m
日本原産種と中国、台湾原産の2種だけしかない。
伐採地や崩壊地によく生えてくるパイオニアプランツ(先駆植物)の性質を持つ。
茎が中空になっており、竹に似ている事から「竹似草」という名前になったそう。(諸説あり)



カギカズラ
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks.
アカネ科 常緑樹
分布 房総半島以南、四国、九州
大きさ 10m
葉の基部上側に鉤がついており、先端を丸め周囲の植物に引っかけて生長するツタ性植物。鉤は規則的に2つ、1つ、2つ、1つとついている。鉤部分は、生薬、漢方薬に利用されている。



クスドイゲ
Xylosma congestum
ヤナギ科 常緑の小高木
分布 近畿以西の本州、四国、九州、沖縄
高さ 5~15m
兵庫県版レッドデータブック2020 Cランク 準絶滅危惧
幹や枝から、枝が変化した鋭い大きな棘が複数でている。
名前の由来は「クスド」はハリネズミの古名「クサフ」から、「イゲ」は棘を意味し、クサフ+イゲがら変化した説がある。




レモンエゴマ
Perilla citriodora
シソ科 一年草
分布 宮城県以南の太平洋側、四国、九州
高さ 20~90cm
在来種。葉を揉むとレモンのような香りがする。精油を抽出し、香料に利用される。

ヤブニッケイ
Cinnamomum yabunikkei
クスノキ科 常緑高木
分布 本州(福島県以南・北陸地方以西)、四国、九州、沖縄 自然分布は近畿以南から沖縄まで
高さ 10~20m
葉はコクサギ型葉序で、葉が左右2枚ずつ互生してつく。葉を揉むとシナモンのような香りがある。月桂樹の代用に煮込み料理などに用いる。

シロダモ
Neolitsea sericea
クスノキ科 常緑高木
分布 山形県と宮城県以西、四国、九州、南西諸島
高さ 2~3m
葉は長楕円形で3行脈で互生し、若葉は帯白色から黄褐色の毛で覆われている。枝先に車輪上に集まり、下垂してつく。葉の裏が白いことから、シロダモとされる。

ボタンズル
Clematis apiifolia
キンポウゲ科 落葉つる性半低木
分布 本州、四国、九州
長さ 2~4m
葉は、1回3出複葉で対生する。花期は8~9月で、茎の先端や葉腋から3出集散状の花序を出す。

リンボク
Prunus spinulosa
バラ科 常緑樹
分布 本州関東以西、四国、九州、南西諸島
高さ 5~10m
日本固有種。
同名のリンボク(学名:Lepidodendron)という石炭期(後期デボン期)に栄えた化石植物があるが、無関係である。
樹齢が低い木の葉は、ヒイラギの葉に似ており鋭いトゲがあるため、別名ヒイラギガシというそう。

ナツフジ
Wisteria japonica
マメ科 つる性落葉木本
分布 日本固有種 関東地域南部以西
大きさ
花期は7~8月で、白い蝶形花で、総状花序が垂れ下がる。果実は豆果で、熟すと種子を飛ばす。
つるは左肩上がりに巻く。



ムラサキシキブ
Callicarpa japonica
シソ科 落葉低木
分布 北海道 道南、本州、四国、九州、琉球列島
高さ 2~3m
花期は6~7月ごろ、小さな淡紫色の花が咲く。果期は10月ごろで、熟すと紫色になる。果序枝は葉腋のすぐ上から出ている。
紫色に熟す重なり合った実を京で「紫重実(ムラサキシキミ)」と呼び、平安時代の紫式部に例えたことが命名の由来だとか。

コアカソ
Boehmeria spicata
イラクサ科 落葉小高木
分布 本州〜九州
高さ 1m
コアカソとよく似たクサコアカソがあり、見分け方は鋸歯の数で前者は鋸歯が10以下、後者は10~20対ある。
湿った場所や田んぼの畦などでよく見られる。
アカソは、茎の赤い麻の意で命名されており、古代にはカラムシと同様に繊維を利用していた

ヤマボウシ
Cornus kousa
ミズキ科 落葉小高木
分布 東北以南、四国、九州、琉球諸島
高さ 5~10m
花期は5~7月で、花形はハナミズキによく似ている。
果期は9~10月で、果実は集合果果実は食用でき、生食のほか果実酒にも適している。若葉も食用される。果実の形がクワに似ているため、別名ヤマグワと言われる。

イヌザンショウ
Zanthoxylum schinifolium
ミカン科 落葉低木
分布 本州(秋田・岩手県以西)、四国、九州
高さ 1~3m
サンショウに似ているが、香りが弱く、香辛料にはあまり使われない。山椒よりも花期が遅く、7~8月ごろ。トゲは互生しており、対生するサンショウと見分けられる。
果実を煎じた液や葉の粉末は漢方薬に利用される。

バクチノキ
Prunus zippeliana
バラ科 常緑高木
分布 本州(関東以西)、四国、九州、沖縄
高さ 10~15m
灰褐色の樹皮は、樹齢を重ねるとウロコ状に剥離し続け、オレンジ色の幹肌が現れ、独特な斑模様を描く。
博打に負けてみぐるみ剥がされる様子に例えて命名されたそう。
葉に含まれる青酸を含むバクチ水は、咳止めや鎮痛鎮痛薬として利用される。
樹皮は香りがあり、染料にもなる。



ヤマブキ
Kerria japonica
バラ科 落葉低木
分布 北海道南部、本州、四国、九州
高さ 1~2m
樹木に分類されるが、茎は細く柔らかく、根元から叢生して株立ち状になる。
細くしなやかな枝が風に吹かれて揺れ動く姿から「山振(ヤマブリ)」と呼ばれ、これが転訛したとされる。
花期は4~5月で、その年に伸びた枝の先端に一輪ずつ、山吹色の花を咲かせる。

ナチシダ
Pteris wallichiana
ウラボシ科 常緑性
分布 千葉県以西、四国南部、九州、琉球列島
高さ 1m
草丈が1mを超え、葉の全長は2mにもなる大型のシダ類。葉全体の形が鳥足状に五角形になるのが特徴。和歌山県の那智で発見されてことから命名されたそう。
若葉を食用する地域もある。鹿は毒成分により食べないが、人間は、あくぬきをしてして可食することが出来る。

エゴノキ
Styrax japonicus
エゴノキ科 落葉小高木
分布 北海道 道南〜沖縄まで
高さ 15m
エゴノキは毒性があり、果実を口に入れると喉や舌を刺激して「えぐい(えごい)」ことに由来し命名されているそう。
地域によっては、この毒性を使い毒流し漁に使われている。
花を手で揉むと泡立つため、「セッケン花」「シャボン花」と呼ばれることも。
花や実は、長い花梗から下垂してつく。



ウドカズラ
Ampelopsis leeoides
ブドウ科 つる性落葉木本
分布 紀伊半島と山口県、四国、九州
兵庫県版レッドデータブック2020 Aランク 絶滅危惧Ⅰ類
他の樹木に覆い被さるように蔓を伸展させる。
種羽状の複葉と対生してのびる巻きひげは、途中で分枝してさらに伸び10cm以上にもなる。

和泉層群
和泉層群は、中央構造線の北側に沿って細長く分布している中世代白亜紀後期の地層。この地層は左横ずれ断層運動にともない、溝のように落ち込んでできた海にたまった地層で、礫岩、砂岩、泥岩からなる。