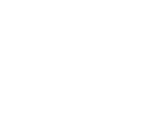植生の調査_File03_慶野松原
2025.6.25
Researchの概要
慶野松原(けいのまつばら)は、南あわじ市の松帆古津路から松帆慶野にある松原である。1928年に国の名勝に指定。1955年には瀬戸内海国立公園に指定されている。
松林も観察ポイントだが、主に砂浜や礫浜に見られる海岸植物を調査する。
Keino Matsubara is a pine grove located in The pine grove extending from Matsuhō Kotsuro to Matsuhō Keino in Minamiawaji City. It was designated a national Places of Scenic Beauty in 1928 and became part of Setonaikai National Park in 1955.
While the pine forest itself is an observation point, the primary focus is surveying coastal plants typically found on sandy and gravel beaches.
調査日2025年6月24日

国土地理院作成の地図を加工して掲載

クロマツ
Pinus thunbergii
マツ科 常緑針葉樹
分布 北海道南部、本州、四国及び九州
高さ 20~40m
駐車場から海岸への入り口にある老松。
樹齢100年は優に超える立派で、樹形がユニークな黒松。
江戸時代より松原は徳島藩の所有として松林が育成されていたことから、樹齢数百年と思われる松も残っている。
松林の中に、マツグミが寄生しているものも見られた。
*マツグミとは、ヤドリギのように松を宿主にする寄生性の樹木。

コマツヨイグサ
Oenothera laciniata
アカバナ科 多年草
分布 本州、四国及び九州、稀に北海道
高さ 20~60cm 匍匐性
6月ごろ淡黄色の花が咲き、萎れると赤く変化する。



ハマボウフウ
Glehnia littoralis
セリ科 多年性草本
分布 北海道から南西諸島にかけて各地の海岸砂地
高さ 10~20cm
柔らかい若葉は、香り高く高級食材として食される。根は漢方薬に使われる。
花期は5~6月で、写真は、花が終わり若い果序の状態である。

ハマゴウ
Vitex rotundifolia
シソ科 落葉低木
分布 本州、四国、九州、沖縄 海岸砂地に群生
高さ 1mほど
花期は7~9月。調査日は6月だったがところどころ紫色の花が開花が始まっていた。葉は対生し、両面に毛があり、裏面は特に銀白の柔らかな毛で覆われている。ハマゴウが潮風や乾燥に耐えるのはこの毛による。 花や葉に芳香があり、古くは線香の材料として使われていた。
実にも強い芳香があり、かつて貴族が集めて枕にして使用していたとか。灰汁は染料に使える。



ハマボッス
Lysimachia mauritiana
サクラソウ科 越年草
分布 北海道から沖縄 海岸の砂地、崖地
高さ 10~40cm
漢字表記は、「浜払子」で、花の咲く様子が仏具の払子(ほっす)に似ていることが由来。
花期は5~6月で、白い花が咲く。写真は花が終わり、果実をつけ始めたころ。

コウボウムギ
Carex kobomugi
カヤツリグサ科 多年草
分布 北海道西岸から琉球列島 砂浜に生育する、代表的な海浜植物
高さ 20cmくらい
豊かな砂浜に生えるといわれ、長く匍匐茎を伸ばし、各所から地上に茎を出しやや疎な群落を作る。古い葉鞘の繊維が、ほぐすと筆のような形であることが、コウボウムギの名前の由来である。
雌雄異株で雄花序の方が雌花序より細い。



アメリカネナシカズラ
Cuscuta campestris
ヒルガオ科 一年草
分布 北アメリカ原産 日本全国に分布
高さ 草丈50cmほど
つる性の寄生植物で、葉緑素がなく、全体的に淡黄色。
他の植物に巻き付き寄生根から養分を吸収し、小突起状の吸盤で絡みついて生長するつる性植物。
一部、茎の途中が大きく膨れているのは虫えいである。



テリハノイバラ
Rosa luciae
バラ科 常緑つる性低木
分布 本州、四国、九州、琉球諸島 海岸、草原、河川敷など
高さ 0.5~1m
在来種で、日当たりの良いところに生える。
葉は皮質で厚く、表面に艶があり(照り葉)、縁には洗い鋸歯がある。枝を匍匐して長く伸ばし、枝は無毛で棘がある。
花期は6~7月で、白色、一部薄いピンク色の芳香のある花をつける。



ハマナデシコ
Dianthus japonicus
ナデシコ科 多年草
分布 本州〜九州、琉球諸島 海岸
高さ 15~50cm
日本固有種。主要な生育地は太平洋側の海岸の岩場や砂浜。
花期は6~11月で、茎の頂上部に密に集まって紅紫色の花を咲かせる。
葉は厚くて光沢があり、対生で柄はなく、ほとんど茎に合着する。

ウンラン
Linaria japonica
オオバコ科
分布 北海道から九州(日本海側 瀬戸内海、大平洋側は千葉以北) 海岸砂浜
高さ 20~30cm
絶滅危惧I類Aランク 兵庫レッドデータ 2020
慶野松原でも1ヶ所でしか見つけられなかった。ハマゴウ、テリハノイバラと混生している。
葉は厚みがあり丸く、茎がほふくする宿根草。
ウンランは漢字で「海蘭」と書き、海辺に生える蘭に似た花を表している。
花期は8~10月で、花は上部の短い総状花序につく。花冠は仮面状で黄白色、花喉部は黄橙色。

ホコガタアカザ
Atriplex prostrata
ヒユ科 一年草
分布 欧州原産 日本全土 海岸砂浜
高さ 20~80cm
葉は下部では対生し、上部では互生する。下部の葉は正三角形に近い矛形で、上部では細長くなる。雌雄同株で花期は9〜11月。
よく似た仲間の在来種のハマアカザは、葉が三角状卵形で基部がくさび形となっている。



ハマエノコロ
Setaria viridis var. pachystachys
イネ科 一年草
分布 北海道〜九州の海岸
高さ 15~25cm
日当たりの良い海岸や岩場に生える。
エノコログサの変種で、背丈を低く穂も小さく、塩風に絶えられるように育つ。穂が小さく、垂れ下がらないで直立する。
茎は分けつして叢生し、基部はほふく状になって横に広がる。